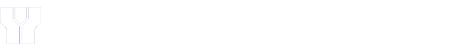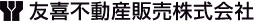建物賃借権の譲渡と建物の転貸②
2.賃借権譲渡・転貸の法的な制約
賃貸借契約は、貸主と借主の信頼関係に基づく継続的な関係が生じている契約であって、目的物の使用・収益の仕方は人によって異なります。
貸主側から見ればだれでも使ってよいというわけにはいきません。
借主その人に着目して貸すという側面が強い契約です。
そこで、民法は、「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、または賃借物を転貸することができない」と規定し(同法第612条第1項)、もし、これに違反して貸主に無断で譲渡または転貸をし、第三者に使用・収益をさせたときは、貸主は賃貸借契約の解除をすることができる旨を定めています。(同条第2項)
そして、このことについて、借地借家法は何ら特別の規定を設けていません。
もっとも、無断譲渡、無断転貸を理由に貸主が契約を解除できるのは、第三者がその建物を使用・収益し始めたとき以降であって、借主が第三者と賃借権の譲渡または転貸の契約を締結しただけでは、契約違反ですが、まだ賃貸借契約の解除をすることはできません。
なお、借地契約に関連する問題ですが、借地人が自ら所有する建物を第三者に賃貸することは、借地の転貸とはならないと解するのが通説・判例です。
したがって、借地人が借地上の建物を第三者に賃貸する場合、法的には地主の承諾は要りません。
3.判例による解除権行使の制限
(1)最初の最高裁判例
賃借権の無断譲渡、転貸を行い、第三者に使用・収益をさせた場合は、上記のとおり貸主が契約を解除できるといっても、厳格にこの原則を適用して、貸主が実質的に何の損害を受けない場合にも自由に賃貸借を終了させることができるのは不当です。
そこで、判例により貸主の解除権を制限する理論が確立しています。
最高裁判所のリーディングケースは、土地の賃貸借に関するものでしたが、地主に実害のほとんど生じない土地の転貸がなされた事案において、「賃借人が賃貸人の承諾なく第三者をして賃借物の使用収益をなさしめた場合においても、賃借人の当該行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合においては、賃貸人は、民法第612条第2項により契約を解除することができない」と判示しました(最高裁判例・昭和28年9月25日)
この「背信的行為と認めるに足らない特段の事情がある場合は解除できない」という理論は、その後の裁判の判断基準になっています。
(2)建物賃貸による解除を認めなかった最高裁判例
上記(1)の判断基準によって、建物の無断転貸を理由とする貸主からの契約解除を認めなかった最高裁の判例を紹介します。
店舗用建物の借主が貸主の承諾を得ないで転貸しましたが、この転貸が借主と第三者との共同経営契約に基づくもので、転貸部分は建物のごく一小部分にすぎず、
その共同経営のために据え付けられた機械は移動式で建物の構造にはほとんど影響がなくその取り除きも容易で、
しかも転借人はこの建物に居住するものではなく、また建物所有権は貸主にあるが、その建築費用、増改築費用、修繕費等の大部分は借主が負担し、貸主が借主から多額の権利金を受けているという事案について、最高裁は、本件の諸事情からみて、この転貸は貸主に対する背信行為と認めるに足らない特段の事情があるものであるとして、貸主の行った契約解除は無効であるとしました(最高裁判決・昭和36年4月28日)
結局、貸主は無断譲渡、転貸があれば解除ができる、しかし借主が背信的行為に当たらない特段の事情を立証できれば、解除の効力が認められないということになります。
もっとも、現実の事例で、背信的行為に当たらないとして解除が認められないケースは必ずしも多いわけではありませんが、その例としては、同居の親族が賃借権を譲り受けたり、転借し、利用の主体に実質的には何ら変更がないケースが挙げられます。
あるいは、借主が個人名義であったが、その個人が法人化して名義が変わったケースで従来と実質的に変化はないようなときも同様と考えられます。
(3)賃借権の無断譲渡による解除を認めなかった最高裁判例
また、形式的には賃借権の主体は変わらないが、会社の役員や資本構成に変動があり、使用・収益の主体が変更されたケースについて、そもそも賃借権の譲渡に当たらないという理論構成で解除の効力を認めなかったものもあります。
それは、借主が小規模・閉鎖的な有限会社で、実質的な経営者が交替したケースについて「会社の構成員や機関に変動が生じても、法人格の同一性が失われるものではないから賃借権の譲渡には当たらない」としています。
以上をまとめると、たとえ賃貸借契約書に「賃借権の無断譲渡または賃借建物の無断転貸をしたときは、貸主は催告なしに契約を解除する」旨の条項があったとしても、あらゆるケースにそれが当てはまるのではなく、その借主のその行為が背信的行為と認めるに足りる事情、すなわち、前述した信頼関係を破壊する程度のものかどうかを実質的に判断しなければならないということです。