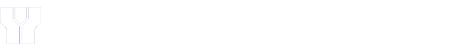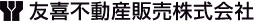2022.08.01
修繕をめぐるトラブル①
1.修繕義務を負うのはどちらかー民法の原則ー
建物の修繕義務を負うのが貸主なのか借主なのかについては、民法に明文の規定があります。
「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」(民法第606条第1項)と、貸主の義務であることがはっきりと定められています。
賃貸借は、貸主が借主に対し賃貸目的物の使用収益をさせることを約し、借主がその対価として賃料を支払うことを約する契約です。
貸主は、いわば契約の効力として目的物を使用収益させる積極的義務を負担し、その義務の一内容として、目的物の破損、毀損によって目的物の使用収益に支障が生じたときは、これを修繕すべき義務を負担しているわけです。
もっとも、これは民法の原則であって当事者間に特約がなければ、このとおりになりますが、当事者間の合意で、これと異なる特約をすることが可能です。
2.修繕義務を負う範囲
民法には、どのような場合に、どの範囲まで義務を負うのかについて、明確な規定はありません。
一般的にいえば、修繕が必要な場合で、かつ修繕が可能な場合にその義務が発生するとされています。
「修繕が必要な場合」とは、その目的物を修繕しなければ、借主が契約の目的に従って使用収益をすることができない状態のことをいいます。
具体的にどの程度のときに使用収益できない、といえるのか判断の難しいものもありますが、契約の目的、使用の方法・程度、通常予想される程度の使用方法などを基準として、少しでも通常の使用に支障が生ずる場合は、修繕の必要があると考えるべきでしょう。
また、建物が地震、火災等により倒壊または焼失してしまい、建物としての効用が失われたときは、貸主の使用収益させる義務は消滅し、修繕義務は生じません。
修繕が全部不能の場合は、貸主は使用収益させる義務を免れ、借主は賃料支払義務を免れることになります(民法第536条第1項)。
一部が不能の場合は、借主の使用収益が可能な部分の全体に対する割合に応じて、借主は賃料の減額を請求できることになります。
修繕が、技術的・物理的観点からみて可能でも、それに要する費用が建物を新築するのと同じくらいかかるという場合は、経済的観点から修繕不能とみるべきでしょう。
また、建物の耐用年数がほぼ終わりに近い場合に、貸主に大修繕を要求することができるのかという問題があります。
これが可能であれば、建物には「朽廃」ということはなく、借主は無制限に賃貸借を継続させることができてしまいます。
判例では、朽廃の時期が近くなり、大修繕の必要がある建物について(旧)借家法第1条の2に規定する、解約申入れに必要とされる「正当事由」を肯定し、貸主からの解約申入れを認めたものがありますが、これは、そのようなケースにおいては修繕義務を認めないということです。
なお、修繕を必要とする破損・毀損状態が借主の責に帰すべき事由(故意または過失)によって生じた場合、借主に損害賠償義務が生ずることは当然としても、その場合でも貸主に修繕義務が生ずるかどうかについては、学説上見解が分かれています。
信義則上、修繕義務は生じないという考え方が有力です。
3.修繕についての借主の協力義務
修繕義務は、貸主の義務であるとともに、自己の所有建物を修繕することは自らの権利でもあります。
したがって、貸主が建物の保存のために必要な修繕をしようとする場合には、借主はこれを拒むことができないこととされています(民法第606条第2項)。
借主がこの義務に違反したときは、債務不履行となり、賃貸借契約の解除原因となると解されています。
民法は借主の立場も考え、貸主が借主の意思に反して保存行為である修繕をしようとする場合において、そのため借主が賃借した目的を達することができないときは、借主から賃貸借を解除することができることとしています(民法第607条)。
この規定を利用して、嫌がらせの修繕行為を行って借主を追い出そうとしても、それは認められません。そのような修繕は、建物の保存のための必要な修繕とはいえず、上記の関係条文の適用を受ける法律関係といえないからです。